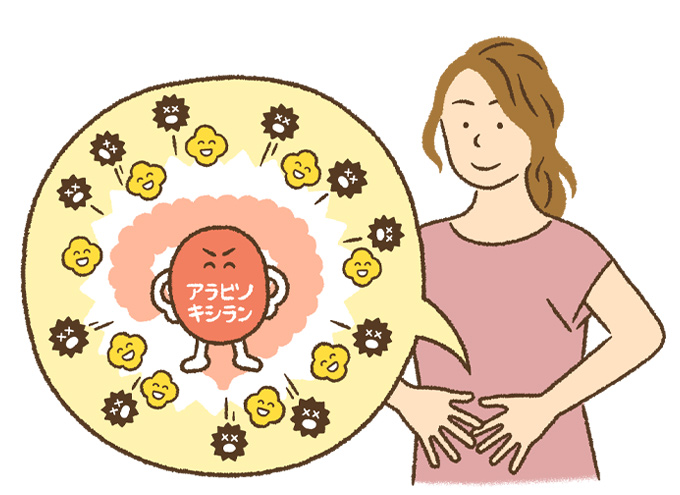実は関係が深い長寿と食物繊維 ①(全2回)
長寿を左右するのは腸内細菌?カギは食物繊維

同じ年齢なのに、見た目や体力に違いがあるなあ……と感じたことはありませんか?人によって老化のスピードが異なるように見えるのはなぜでしょうか。最近の研究では、その原因に腸内細菌が関わっていることがわかってきました。

同じ年齢なのに、見た目や体力に違いがあるなあ……と感じたことはありませんか?人によって老化のスピードが異なるように見えるのはなぜでしょうか。最近の研究では、その原因に腸内細菌が関わっていることがわかってきました。
腸内細菌はバランスと多様性が大切
腸には40~100兆個もの細菌がすみつき、その種類は1000種類ともいわれており、それらの集合体を腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)といいます。腸内フローラとも呼ばれるこの腸内細菌叢は一人ひとり異なります。その人にどんな腸内細菌がすみつくかは、母親の胎内にいるときから3歳ぐらいまでにほぼ決まり、その後大きく変わることはありません。しかし、ベースとなる腸内細菌は変わらなくても、腸内細菌叢のバランスは食事や生活習慣によって良くも悪くも変化していきます。
腸内細菌叢のバランスが良い人ほど、糖尿病や心筋梗塞など生活習慣病のリスクが低いことが研究により示されており、それには、腸内細菌がつくりだす短鎖脂肪酸が免疫機能を高めたり、炎症を抑制したりすることが影響していると考えられています。つまり、腸内細菌叢のより良いバランスを保つことは、健康と密接に関わっているのです。
ただし、より良いバランスとは「悪い菌を減らして良い菌を増やせばいい」という単純なものではありません。腸内細菌叢は一つのコミュニティとして互いに影響し合っているため、増えすぎると悪影響を与える菌であっても何かしらの役割を担っており、排除すれば別の菌が悪さをします。コミュニティ全体でバランスを保たねばなりません。それには、菌の数だけでなく種類も多いほうが良いとされており、腸内細菌の世界でも多様性が大切だといえるでしょう。
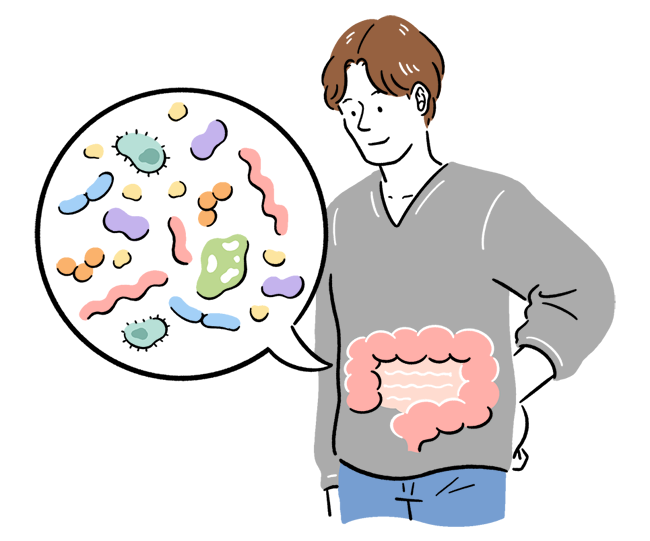
腸内細菌と老化の関係
では、腸内細菌と老化はどう関係しているのでしょうか。
腸内細菌叢のバランスは、加齢によっても変化します。年齢が高くなるにつれて悪い菌が徐々に増え、多様性が低下し、乱れていきます。しかし、前述の通り腸内細菌叢のバランスは食事や生活習慣によって変えることができるため、それらを改善し、腸内細菌叢を若い状態に近づけることで、さまざまな病気や不調のリスクを低くすることができ、結果的に老化スピードを緩め、健康寿命を延ばすことにつながります。
老化研究の分野において、腸内細菌は年齢では測れない生物としての衰えを測る「老化の指標」の一つとして、近年関心が寄せられています。
腸年齢をチェックしてみよう!
腸年齢とは、腸内細菌叢の状態を実年齢に置き換えて示したものです。腸年齢が若いということは、腸内細菌叢のバランスが良い状態であるということ。自分の腸の若さを知るために、まずはチェックしてみましょう。
結果を目安に、食生活や生活習慣を少し見直すきっかけにしてみてください。
健康的な腸内環境のカギは食物繊維
腸内細菌叢のバランスには、環境やストレスなどいくつもの要因が影響しますが、もっとも大きく影響するのは食事です。特に、人の消化酵素では分解されず大腸にすむ腸内細菌のもとまで届く「食物繊維」は欠かせない要因です。
中でも注目すべきは「発酵性食物繊維」。発酵性食物繊維は、良い菌のエサとなり増殖させるとともに、短鎖脂肪酸を産出させます。短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えるほか、腸粘膜を守るなど、腸内環境を整えてくれます。さらには血糖値や脂質のコントロール、全身の炎症抑制にも関与するといわれています。
発酵性食物繊維を多く含む食品には、豆類、イモ類、全粒穀物、キノコ、ゴボウなどの野菜、そしてキウイやリンゴなどの果物があります。おすすめは主食を工夫すること。例えば、玄米ご飯、麦めし、雑穀ご飯、全粒粉のパンなどを取り入れ、1日3食のうち1食は主食を「茶色」系統(未精製の穀類)にすると良いでしょう。白米や精製小麦のパン、麺類は食物繊維が少なく、かといっておかずだけで1日の十分な量を摂るのは難しいためです。
日本人は欧米人に比べ食物繊維の摂取量が少なく、特に若い世代は目標量を大きく下回っているのが現状です(「日本人の食事摂取基準2025年版」策定検討会報告書)。長寿のために、毎日の食事で意識的に食物繊維を摂ることを心がけましょう。

日本人は欧米人に比べ食物繊維の摂取量が少なく、特に若い世代は目標量を大きく下回っているのが現状です(「日本人の食事摂取基準2025年版」策定検討会報告書)。長寿のために、毎日の食事で意識的に食物繊維を摂ることを心がけましょう。
長寿を目指す第一歩は、腸内細菌のエサ=発酵性食物繊維を意識して摂ること。毎日の食事のちょっとした工夫で腸内細菌叢は若返らせることができます。
次回は、京丹後地域に学ぶ、健康長寿のためのライフスタイルをご紹介します。
このシリーズ(全2回)の他の記事を読む
- <参考書籍>
- ・内藤裕二. 健康の土台をつくる腸内細菌の科学. 日経BP, 2024.
<監修>
内藤裕二
京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座 教授